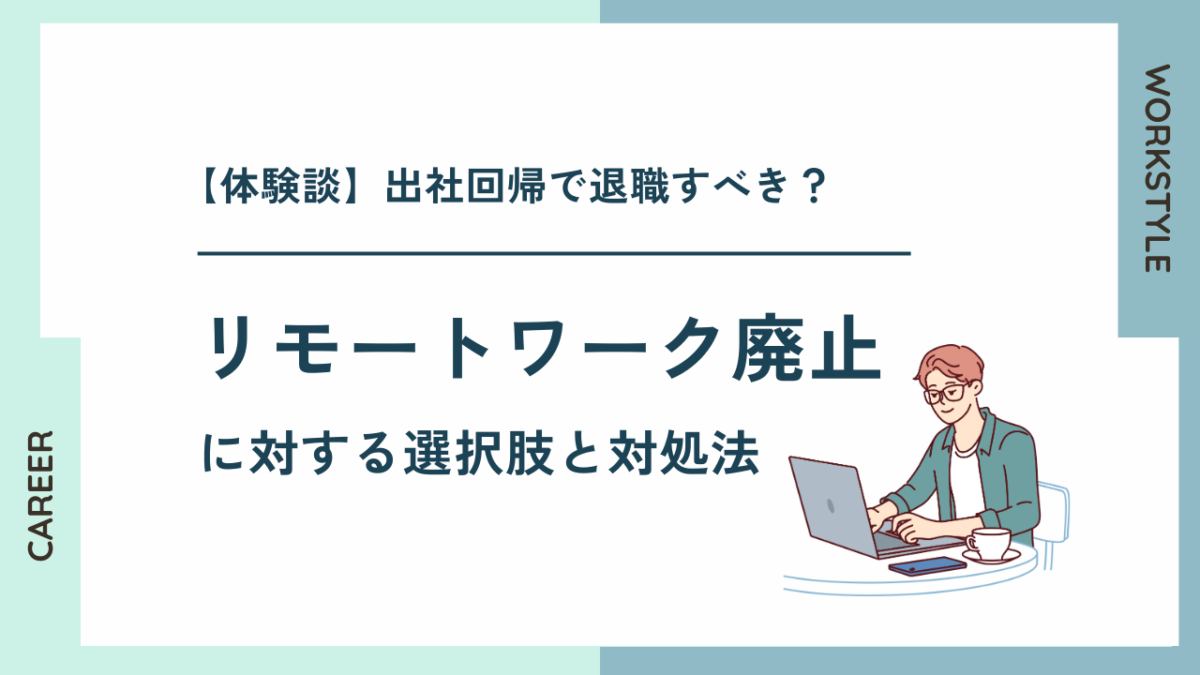コロナ禍で急速に普及したリモートワーク。最近では多くの企業で「出社回帰」の傾向が見られます。場所に縛られない自由な働き方に慣れてきた矢先、勤務先から出社を要請され、戸惑いや不満を感じている方も多いでしょう。「通勤時間がない快適さを手放したくない」「育児や介護との両立が難しくなる」といった理由から、退職や転職を真剣に考え始める人も少なくありません。
そこで今回は、出社回帰を機に退職や転職を検討する働く人々の本音、出社回帰に直面した際の具体的な選択肢と対処法について詳しく解説します。勤務先の出社回帰を機に実際に退職した人の体験談も紹介しますので、後悔しない選択をしたいと考えている方は、ぜひ参考にご覧ください。

勤務先の出社回帰で退職を検討する人も
コロナ禍が落ち着きを見せ始めるとともに、多くの企業でオフィスへの出社を要請する動きが活発化しています。しかし、一度リモートワークのメリットを感じた人の中には、退職や転職を考える人が増えています。
企業が出社回帰を求める理由
企業が従業員に出社を求める背景には、次のような理由があります。
◆コミュニケーションの活性化
対面でのコミュニケーションは、意思疎通が円滑に進むので、アイデア交換が生まれやすくなると考えられています。特に、部署間の連携や新入社員の育成の面では、直接顔を合わせる重要性を指摘する声があります。
◆チームの一体感の醸成
同じ空間で働くことで、チームとしての連帯感が高まると期待されています。一体感が高まることで協力体制が強化され、組織全体の目標達成につながると考えられています。
◆生産性の向上
企業によっては、従業員の働きぶりを直接確認できないリモートワークに対し、オフィス勤務のほうが管理しやすく、生産性が向上すると考えます。情報セキュリティの観点からも、機密情報を扱う業務はオフィスで行うほうが安全だと判断されるケースもあります。
これらの理由は、企業側の視点に立てば合理的ですが、働く人にとっては、必ずしも納得できるものではないかもしれません。
出社要請で退職や転職を考える人は約16%
国土交通省が令和5年に行った「テレワーク人口実態調査」によると、勤務先が出勤を指示・推奨した場合の行動について、テレワーク実施者の回答は以下のとおりでした。
- 「テレワーク可能な働き方ができるよう勤務先と交渉」:16.3%
- 「転職又は独立起業を検討」:7.4%
多くの人が、今後もテレワークを継続したいと考えていることがわかります
出典:国土交通省「令和5年度 テレワーク人口実態調査」
出典:公益財団法人 日本生産性本部「第13回 働く人の意識に関する調査」
公益財団法人日本生産性本部が2023年に実施した「第13回 働く人の意識に関する調査」では、勤め先でテレワークが廃止・制限された時どのように行動するかという質問に対し、テレワーク実施者の回答は以下のとおりでした。
- 「退職、転職を検討する(もしくは既に退職、転職した)」:16.4%
- 「今の勤め先で継続して働くが、時短勤務など働き方の変更を検討する(もしくは検討した)」:24.9%
テレワーク実施者の4割近くの人が、出社回帰の際に働き方を見直そうと考えていることがわかります。
柔軟な働き方を求め転職する人が増加中
これらの調査結果から、企業が出社回帰を進める一方で、従業員の多くはリモートワークの継続を望んでおり、そのギャップが退職や転職を考える一因となっている実態がうかがえます。転職活動の現場で求職者の声を直接聞く、人材派遣・紹介サービス『はたかな』のキャリアアバイザー坪谷さんも、「柔軟な働き方を求めて転職する人が増えている」と話します。
フル出社ではなくても、出社日数を増やしている企業が多くなってきている印象です。その影響で、リモートワークを活用して家事・育児をしていた20〜30代が、柔軟な働き方を求めて転職を選ぶケースが増加していると感じます。
フレキシブルな働き方を求める子育て世代向けの転職サービス『はたかな』でも、男性の利用者も増えてきました。
また、介護のためにリモートワークを希望される方も、以前より多くなったなと感じます。
キャリアアドバイザー 坪谷さん
出社回帰を理由に退職すべきか?比較ポイント
勤務先から出社回帰を要請されたときは、出社とリモートワーク、それぞれのメリット・デメリットを整理し、自分にとって何が最も大切なのかを見極めましょう。
出社のメリット・デメリット
出社のメリットとデメリットは、以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
| ・円滑にコミュニケーションをとれる ・チームの一体感が向上する ・オンオフを切り替えやすい ・アイデアが生まれやすい ・充実した環境で働ける | ・通勤に労力がかかる ・時間の制約がある ・出社に伴う費用がかかる ・周囲の話し声などで集中できない場合がある ・感染症のリスクがある |
出社のメリット
◆円滑にコミュニケーションをとれる
対面での会話は、表情や声のトーンからニュアンスが伝わりやすく、誤解が生じにくいです。気軽に相談や雑談ができるため、情報共有やアイデア出しも活発になります。
◆チームの一体感が向上する
同じ空間で働くことで、連帯感が生まれやすくなります。困っている同僚をサポートしたり、逆に助けてもらったりする中で、一体感が高まります。
◆オンオフを切り替えやすい
通勤によって、仕事モードへ切り替えやすくなります。自宅とは違う環境で働くことで、メリハリが付き、集中力を維持しやすいと感じる人もいます。
◆アイデアが生まれやすい
他部署の人との雑談や、オフィス内で見かける情報から、新しい知識やアイデアを得やすくなります。
◆充実した環境で働ける
高速なネットワーク回線、大型モニター、高性能な複合機など、自宅よりも整った環境で仕事ができる場合があります。
出社のデメリット
◆通勤に労力がかかる
満員電車での通勤や長時間の移動は、肉体的・精神的な負担となります。通勤時間があることで、プライベートな時間が削られると感じる場合もあります。
◆時間の制約がある
始業・終業時間に合わせて行動する必要があるので、育児や介護など、家庭の事情との両立が難しくなる場合があります。
◆出社に伴う費用がかかる
交通費(会社負担の場合を除く)、昼食代、オフィス用の洋服代など、出社に伴う費用が発生します。
◆周囲の話し声などで集中できない場合がある
オフィスの環境によっては、周囲の話し声や電話の音などが気になり、集中できない場合があります。
◆感染症のリスクがある
多くの人が集まるので、感染症にかかるリスクが高くなります。
リモートワークのメリット・デメリット
リモートワークのメリットとデメリットは、以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
| ・通勤時間がかからない ・柔軟な働き方ができる ・集中しやすい環境を整えられる ・出社に伴う費用を削減できる ・好きな場所に住める | ・コミュニケーションを取りにくい ・運動不足になりやすい ・自己管理能力が必要 ・自分で設備や環境を整えなければならない ・情報の格差や評価への不安が生まれやすい |
リモートワークのメリット
◆通勤時間がかからない
通勤時間がなくなることで、その時間を家事やスキルアップのインプットタイム、家族との時間などにあてられます。
◆柔軟な働き方ができる
育児や介護など、個人の事情に合わせて働き方を調整しやすく、中抜けして家事をすることも可能です。
◆集中しやすい環境を整えられる
自宅など、自分が最も集中できる環境を選んで仕事ができます。
◆出社に伴う費用を削減できる
通勤費、昼食代、衣服代など、出社に伴うコストを削減できます。
◆好きな場所に住める
オフィスへの通勤が不要なので、住む場所の選択肢が広がります。地方移住なども可能です。
【関連記事】地方移住を成功させる仕事選び|知っておきたい探し方やリモートワークを紹介
リモートワークのデメリット
◆コミュニケーションを取りにくい
テキストのやり取りが中心となり、意図が伝わりにくかったり、気軽に相談しにくかったりするケースがあります。雑談が減るので、孤独を感じる人もいます。
◆運動不足になりやすい
通勤やオフィス内での移動がなくなるため、意識的に運動しないと運動不足になりがちです。
◆自己管理能力が必要
仕事とプライベートの境界が曖昧になり、長時間労働につながったり、逆に集中できなかったりする場合があります。自分でスケジュールを管理し、モチベーションを維持する必要があります。
◆自分で設備や環境を整えなければならない
自宅のネットワーク環境やデスク、チェアなどを自分で整える必要があります。光熱費などの負担も増える可能性もあるでしょう。
◆情報の格差や評価への不安が生まれやすい
オフィスにいるメンバーとの情報の格差を感じたり、自分の働きぶりや成果が正当に評価されているか不安になったりする場合があります。
これらのメリット・デメリットを踏まえ、「自分にとって譲れない条件は何か」「今の会社でその条件は満たせるのか」をじっくり考えてみましょう。
出社・リモートワークのメリット・デメリット、リモートワークに求められるスキルなどについては、こちらの記事もご覧ください。
【関連記事】オフィス出社にメリットはある?リモートワークと比較!ベストな働き方とは
出社回帰によって退職した人の体験談
実際に出社回帰をきっかけに退職を選んだ人は、どのような経緯をたどり、今どのように感じているのでしょうか。
ここでは、勤務先の出社要請により退職したあと、希望の働き方をかなえたTさんの事例を紹介します。
事例紹介:0歳と1歳(当時)の子をもつTさん(30代・男性)の場合
――前職での働き方は?
フルリモートワークで勤務していましたが、コロナ禍が明けると、だんだんと出社頻度を増やしていく出社回帰の流れになりました。小さい子どもがいる家庭や、妊娠している家族がいる家庭などはリモートでもOKと言われていましたが、全社的に出社の方向へ変わってきました。
――退職を選んだ具体的な理由は何ですか?
当時0歳と1歳の年子の子どもがいて、かなり大変な状況でした。リモートワークの仕事に転職して、子育ての時間を少しでも確保したいと考えたのです。
――職場に「リモートワークを増やしたい」などの交渉はしましたか?
いいえ、特にしませんでした。会社の判断で出社を決め、多くの社員が出社している中で、自分だけリモートを増やすという希望は出したくなかったです。仮に希望がかなっていたとしても、少し気まずさを感じたと思います。
――転職先を決めてから退職しましたか?退職後に転職活動を始めましたか?
転職先が決まってから退職したものの、辞めたあとに子どもの持病が発覚し入院することになり、入院期間も定かではなかったため辞退しました。
失業手当をもらい、子育てに集中することにして、落ち着いたタイミングで転職活動を再開しました。
―― 転職活動では転職サイトや転職エージェントを利用しましたか?
転職サイトやエージェントも活用したものの、最終的には自分で転職先を見つけ、決定しました。
――転職した現在、どのような働き方をしていますか?前職で実現できなかった希望は実現できていますか?
基本的に現在の仕事はフルリモートなので、家庭と両立させやすく、希望どおりの働き方ができています。
――転職活動をした中で「やって良かった」と感じるのはどんなことですか?
オンラインスクールで学んだり、副業をいろいろ試したりしました。そのおかげで、直接的にそのポジションに携わるわけではないけれど、少し視野が広がり、仕事にも役立つようになったと感じています。
――退職や転職で「準備しておくべきだったこと」はありますか?
スキルの棚卸・職務経歴書や履歴書の作成は、日々やっておかないと忘れている部分もあるなと反省しました。
職務経歴書の書き方について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
【関連記事】【職務経歴書の書き方】転職の多い人が採用されるための6つのチェックリスト
出社回帰に対する4つの選択肢と対応策
勤務先から出社を求められた場合、いくつかの選択肢が考えられます。それぞれのメリット・デメリットを把握したうえで、自分にとって最適な道を探りましょう。
選択肢1.出社に応じる
最もシンプルな選択肢は、会社の方針に従い、出社勤務に戻ることです。転職活動の手間やストレスもなく、慣れた環境で働き続けられます。対面コミュニケーションがスムーズな面では、やり取りのストレスが減るでしょう。
一方で、通勤のストレスや時間的な制約が生じます。不満を抱えたまま働き続けると、モチベーションが低下するおそれもあります。
選択肢2.部分的な在宅勤務が可能か交渉する
フルリモートが難しい場合でも、週に数日や特定の曜日だけ在宅勤務をするハイブリッドワークを認めてもらえないか、交渉するのもひとつの方法です。通勤の負担を軽減しつつ、対面でのコミュニケーションも確保できるなど、 出社とリモートワークのメリットをともに得られます。
選択肢3.異動や配置転換を希望する
別の部署への異動や配置転換を希望する方法です。現在の部署では出社が必須でも、他の部署や職種であればリモートワーク可能なケースがあります。異動によって、新しいスキルや経験を積むチャンスになる場合もあるでしょう。
選択肢4.退職・リモートワークを継続できる仕事に転職する
現在の会社で希望する働き方が実現できない場合、リモートワーク可能な企業へ転職する選択肢です。転職によって、自分の理想とする働き方を実現できる可能性は高い一方で、収入が変動する可能性も視野に入れておきましょう。
出社回帰で退職を選ぶ前に会社と交渉する際の5つのポイント
「できれば今の会社で働き続けたいけれど、完全な出社回帰は受け入れがたい」と考えるなら、退職を決断する前に、会社と交渉してみる価値はあります。交渉を成功させるためには、以下のポイントを押さえて、事前準備をしておきましょう。
1. 自分の要望を明確に整理する
まず、「自分はどうしたいのか」を具体的に整理します。単に「フルリモートがいい」だけでなく、次のように具体的な希望条件を明確にしましょう。
- 週に〇日はリモートワークをしたい
- 〇曜日は在宅勤務にしたい
- フレックスタイムを導入してほしい
最低限譲れないラインと、妥協できるラインを決めておくことも大切です。
2. 在宅勤務でも成果を上げた実績データを用意する
リモートワークに対する会社の懸念点を払拭するには、客観的な実績を示すことが効果的です。「リモートワークでも業務に支障なく、むしろ成果を出せた」と証明するデータやエピソードを準備しましょう。例えば次のようなものが挙げられます。
- リモートワーク下で達成した個人の業務目標
- 担当プロジェクトの納期遵守率や目標達成率
- オンラインでの円滑な対応や連携の具体例
定量的な数値や具体的な成果を示すことで、説得力が増すでしょう。
3. 業界内の他社の状況を調査しておく
業界全体の動向を踏まえて話すことも有効です。同業他社や競合企業が、リモートワークやハイブリッドワークをどの程度導入しているか調査しましょう。「業界内ではハイブリッドワークが主流になっている」「競合の〇〇社はフルリモートを継続している」といった情報があれば、交渉の材料になる可能性があります。
4. 出社によって生じる支障を具体的に伝える
なぜ出社が難しいのか、出社することでどのような支障が生じるのかを具体的に伝えましょう。
- 往復〇時間の通勤や満員電車のストレス
- 育児や介護との両立が困難
- 持病による健康上のリスク
- オフィス環境での集中力の低下
こうした点が業務に影響を及ぼす可能性があると冷静に伝えることで、会社側に理解してもらいやすくなります。
5. 部分的な妥協案も用意しておく
会社側の事情も考慮し、現実的な落としどころを探る姿勢も大切です。そのため、いくつかの妥協案を用意しておきましょう。
- 週〇日、特定の業務のみなど、限定的なリモートワークの許可
- フレックスタイム制や時差出勤の導入
- 試験的なハイブリッドワークの導入
会社側も受け入れやすい現実的な提案を用意することで、交渉が前進する可能性があります。
リモートワーク可能な企業への転職を考える際の注意点
転職活動では、フルリモート勤務を前提とすると、選択肢を狭めてしまうおそれがあります。「月間何日までなら出社できる」などの妥協点をもっておくと選択肢が広がります。また、出社頻度以外にも、以下の点を事前に確認しておきましょう。
- どのようなときに出社が必要となるのか
- 家庭の事情による突発的な事態に理解があるか
- 企業が社員の働き方をどう捉えているのか など
転職エージェントを利用すると、実際にどういった働き方を推進している企業なのかを事前にチェックできます。入社前に聞きにくい質問も、キャリアアドバイザーを通して確認できるので、「こんなはずじゃなかった」といったミスマッチを避けやすいでしょう。
出社回帰による転職のご相談は「はたかな」へ
「出社回帰をきっかけに、今後の働き方を見直したい」
「リモートワークやハイブリッドワークが可能な仕事を探している」
「今の会社と交渉すべきか、転職すべきか迷っている」
このようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ「はたかな」にご相談ください。
「はたかな」は、柔軟な働き方ができるよう伴走する人材紹介・派遣サービスです。一人ひとりの価値観やライフスタイルに寄り添い、自分らしい働き方をかなえられるよう、最適な選択肢をご提案しています。
経験豊富なキャリアアドバイザーが、新しい一歩を全力でサポートしますので、リモートワークやハイブリッドワークのお仕事をお探しの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
出社回帰と向き合い、後悔のない選択を
勤務先の出社回帰の流れに戸惑い、退職や転職を考える人が増えています。退職を選ぶ前に、まずは会社との交渉を試みたり、転職活動における注意点を確認したりして、選択肢を整理しましょう。自分の価値観やライフプランに合った後悔のない選択をするために、転職エージェントなどのサポートを活用するのもおすすめです。